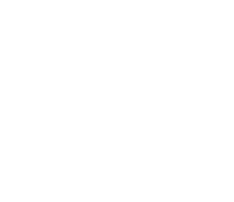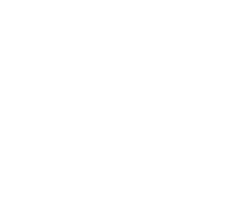B型肝炎ワクチンはB型肝炎の予防接種です。B型肝炎ワクチンは、母子感染の防止、医療関係者の職業感染予防、針刺し事故対策などで広く使われています。
4〜6ヶ月間に3回の接種を行うことで、B型肝炎と将来の肝がんを予防できるとされています。接種は通常皮下注射で行われます。接種量0.25mLから0.5mLです。2016年10月から乳児への定期接種も開始されています。
HBワクチンの接種は世界180か国以上で行われており、ワクチンの中でも最も安全なものの一つです。
乳幼児期に3回の接種を行った場合、ほぼすべての人がB型肝炎に対する免疫(HBs抗体)を獲得することができます。
獲得した免疫は少なくとも15年間持続することが確認されています。20歳代までに接種を行った場合も高い効果が期待できます。
ただし、B型肝炎ワクチンの効果は年齢と共に低下します。例えば40歳を過ぎてからのワクチン接種により免疫を獲得できるのは約80%です。
渡航者はB型肝炎ウイルス感染のリスクにさらされる機会が多々あります。発展途上国では、医療機関における器具の消毒、輸血血液の安全性などが徹底されてない地域も多くあります。不慮の事故や疾病などで医療機関を受診する可能性は誰にでもあり、またB型肝炎ウイルスキャリアの多い地域で医療行為や救援活動に従事する渡航者もいます。さらに、性感染症として伝播することもしばしばあります。